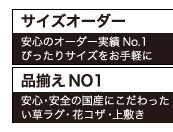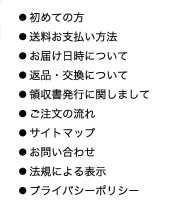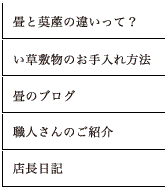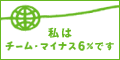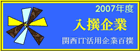古くは古事記に「畳」という言葉が登場しています。この場合は、各種の敷物、またはムシロのようなもののことを指していました。現在のような形になったのは奈良時代で、聖武天皇が使用した木製の台の上に置いて使う「御床畳」[ごじょうのたたみ]が最も古いとされています。
平安時代には、寝殿造りの貴族住宅において、板敷きの床の一部にだけ敷き、寝具、座具として使用していました。
鎌倉時代に入ると部屋に敷き詰める方式が一般化し、江戸時代に入ってから庶民の住宅にまで普及しました。
明治時代に入ると、上流階級では住宅の洋風化が進み、畳の使用が減少しましたが、中流階級以下の住宅ではさらに畳が普及しました。しかし、第二次世界大戦後は、畳を使った和室は一部屋だけという住宅が多くを占めています。
い草と畳にこだわる 【和心本舗】
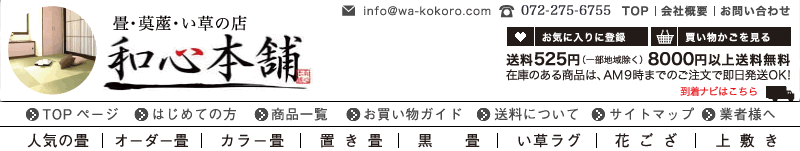 |
||||||||||||||||||||||||||||

|
畳に関する情報 畳の普及と衰退と・・・
|
|||||||||||||||||||||||||||